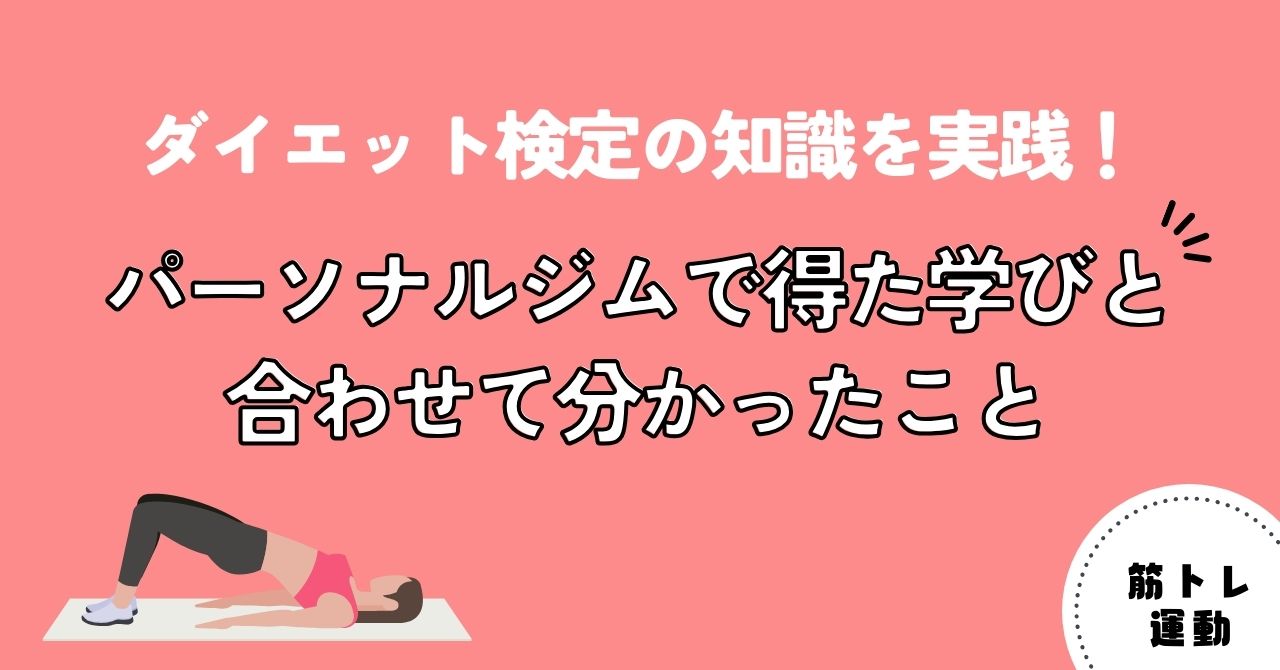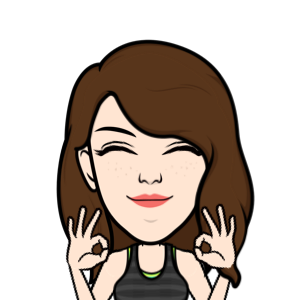
ダイエット検定で得た知識を、パーソナルジムと自宅トレでどう実装したかをまとめました。
「理論どおりにいかない」をどこで調整したか、40〜50代女性でも続けやすい形に落とすコツを体験ベースで紹介します。
目次
検定の知識を“現場”に落としたら分かったこと
資格学習で得た理論は、そのままでは正解でも、日々の生活リズムや体調の波、仕事・家事の都合にぶつかった瞬間に詰まりやすいと感じました。
そこで私が実際にやってみて手応えがあったのが「①朝とトレ後にタンパク質を先に決める」「②負荷は“最後の2回がややきつい”を目安に、その日の調子で下げられる逃げ道を用意」「③週の“型”を先に決めて当日判断を減らす」の3点です。
どれも難しい道具や完璧な気合いはいりません。前者はタンパク質約20g目安を小さく固定するだけで、献立も買い物も迷いが減り、結果的に継続率が上がりました。
負荷はフォームと呼吸を崩さないようにすればOKで、体調が揺れる40〜50代でも“ゼロにしない”を守りやすくなります。
最後にスケジュールは、曜日で役割を決めておくと「今日は何をやる?」の迷いが消え、短時間でも着手しやすいです。理論を現場に落とす鍵は、強さより“仕組み”を先に作ることでした。

PFCは朝とトレ後で先にPを確保すると迷わない
食事設計はPFC(タンパク質・脂質・炭水化物)で考えると整理しやすいのですが、実務では“どこから決めるか”で迷いがちでした。
私がうまく回ったのは「朝とトレ後だけは先にP(タンパク質)を確保する」という小ルールです。
朝は前回の食事から間隔が空きやすく、タンパク質が不足しがちなので卵2個+ヨーグルト、またはプロテイン約20gを先に置くと、その後のF(脂質)・C(炭水化物)は腹具合や予定で微調整するだけで済みます。
トレ後も同様で、P(タンパク質)を固定(例:サラダチキン半分+十割そば少量、プロテイン約20g+果物)すれば、「何を食べるか」で迷う余地が減り、過不足の振れ幅が小さくなります。
先にP(タンパク質)を決めるメリットは、買い物・下ごしらえ・外食時の選択まで一貫してラクになります。忙しい日は“P(タンパク質)だけ達成→残りは夜で整える”と割り切れるので、完璧主義を手放しやすく、結果的にPFCの総量とバランスが安定していきました。
最初は朝とトレ後の2枠だけでOK!小さな固定化が、全体最適に効きます。
負荷設定は「最後の2回がややきつい」目安でOK(日によって下げる)
重さ・回数の正解探しで止まるより、「最後の2回がややきつい」を目安に始めると継続が安定しやすくなりました。
フォームが崩れず、呼吸を止めずに行える重量(または回数)を選び、違和感のある関節は可動域を浅めにします。
体調が揺れやすい日は、回数を2〜3回減らす・重量を1段下げる・テンポをゆっくりにする等で“質”を担保します。
例えば8〜12回×2セットが目安なら、眠りが浅かった日は6〜8回×1〜2セットに、違和感があれば可動域を半分に——といった具合です。
仕上げの2回が「ややきつい」に届かなければ、次回少しだけ重さや回数を足す。逆に張りが強く残ったら、次回は2割下げたり、微調整ループが安全側に働き、積み上がりやすいと感じました。大切なのは“痛みゼロ優先”です。
鏡で姿勢を確認し、肩・肘・膝・腰の位置関係が保てる範囲で行います。
目安をシンプルにすると、日替わりの体調に合わせて続けやすくなります。
週の型を決めて当日判断を減らす(月:下半身/木:上半身など)
「今日は何をやるか」で迷う時間と気力の消耗は、意外に大きなハードルでした。
そこで、週の“型”を先に固定します。例)月:下半身(スクワット系・ヒップヒンジ)、木:上半身(プレス/プル)、土:体幹+可動性、火金:オフor散歩と、ある程度決めました。
各日はメイン2種目+サブ1種目の“2+1”だけ決め打ちして、当日は負荷と可動域だけを体調に合わせて微調整します。
忙しい日や不調日は“短縮版”を標準装備しました(例:各1セット・合計7分)。
どうしても時間が取れない日は「1種目1セットで◯にしてよい」とルール化しておくと、ゼロ日が激減します。加えて、記録は◯/△/×と一言メモのみで、完璧なログではなく“続いた軌跡”を可視化することが目的です。
これにより、「今日は木=上半身だから、この2+1だけやる」で即行動に移せ、意思決定の負担が激減しました。
食事や睡眠の微調整も曜日の文脈で整えやすくなりました。型は季節や仕事量で見直してOKにして、仕組みで迷いを消すほど、継続のハードルは下がります(スケジュールは無理のない範囲で調整してください)。
次は、食事とトレの“具体ルール”を見ていきます。
理論とズレた点/こう直した
本やテキストで学んだことは、とても大事な土台です。でも、そのまま毎日に当てはめると「頭では正しいのに、続かない…」ということが起きました。
私の場合のズレは2つです。①ごはん(糖質)を減らしすぎて力が出ない、②その日のメニューを全部やろうとして疲れてやめてしまう、の2つでした。
そこで考え方を少し変えました。トレーニングの前後だけは少しの主食とタンパク質を先に用意する。運動は“最低ライン”を決めて、できる日だけ増やす。こうした小さな直しで、迷いが減り、続けやすくなりました。下でやり方を詳しく書きます。

糖質を削りすぎ→トレ前後は少量の主食+Pに修正
体重を早く落としたくて、ごはんやパンをほとんど食べない時期がありました。
すると、トレーニング中に力が入らない、終わってから甘い物に手が伸びる、という悪い流れになりました。
そこで「トレ前後だけは少し食べる」をルールにしました。
トレ前30〜60分なら、バナナ半分+無糖ヨーグルト、全粒粉パン1枚+ゆで卵、十割そばを少し+サラダチキン少し、など。お腹が弱い日は消化の軽いものにします。
トレ後は“タンパク質を先に”で、プロテイン1回分や鶏むね少量に、おにぎり半分などを足します。ポイントは“少量”。たくさん戻すのではなく、動くための燃料をちょい足しするだけです。
これでフォームが安定し、過食もしにくくなりました。忙しい日は、常温や冷凍で置いておける物(ツナ、サラダチキン、冷凍そば、全粒パン)を用意しておくと迷いません。
毎回全メニュー完遂→“1種目1セットでもOK”ルールで継続
「計画したメニューを全部やる」を目標にすると、時間がない日や体調がイマイチな日にゼロになりがちです。
ゼロが続くと心が折れて、やめたくなります。そこで“最低ライン”を決めました。
たとえば、その日のメイン種目を一つだけ選んで、8〜12回×1セットできたら合格。元気なら2〜3セットに増やす。不調なら可動域を浅め、重さは1段下げ、ゆっくり動く。
これでもOKにします。やり方はシンプルで、タイマーを7〜10分にセットしてスタート。終わったら手帳に◯/△/×と一言メモ(例:重さ−1段、浅め)を書くだけ。
当日に「何をやるか」は迷わないよう、曜日で大まかに固定しておくと楽です(例:月=下半身、木=上半身)。この“1種目1セットOK”にしてから、ゼロの日がほぼなくなり、合計の回数も増えやすくなりました。大切なのは完ぺきではなく“やめない仕組み”です。
パーソナルジムで補正されたこと
パーソナルジムでは、つぎの3つを強く直されました。フォーム(動き方)/休む入れ方/記録のつけ方です。どれもシンプルですが、続けやすさとケガ予防に直結しました。

フォーム(可動域は“痛みゼロ”を最優先)
はじめは大きく動こうとして、肩やひざに力みが出ていました。トレーナーには「広さよりも安全。痛みゼロの範囲で、小さくてOK」と何度も言われました。ポイントは以下です。
フォームのポイント
- 息を止めない(上げる時に“フッ”、下ろす時に“スー”)
- 肩をすくめない/腰をそらしすぎない
- ひざが内側に入らないように、足先と同じ向き
- 最後の2回だけ少しきつい重さ(余力ゼロはNG)
- 可動域は“気持ちよく動ける”幅で止める
この考え方に変えてから、狙った場所に効かせやすくなり、翌日のつらい張りも減りました。鏡で角度を見る、10秒だけ動画を撮る、などのセルフチェックも役立ちました。痛みやしびれが出たら、その場で中止です。
休養の入れ方(オフは“攻め”)
以前は「毎日やらなきゃ」と思い、同じ部位を連日で動かしていました。今は同じ部位は48〜72時間あけるを目安にしています。
たとえば、月=下半身、木=上半身。合間の日はウォーキングやストレッチだけにします。
休養のポイント
- 眠れない日や強い疲れの日は、重さ−1段/回数−2で実施
- 翌日に強い張りが残ったら、次回は負荷や可動域を2〜3割ダウン
- 水分、タンパク質、炭水化物を少しずつ確保
- 3〜5分のウォームアップ、終わりに軽いストレッチ
「休む=サボり」ではありません。オフは体を強くするための準備時間だと学びました。
記録のつけ方(“最小”で十分)
完璧なノートは続きません。教わったのは“最小の5点セット”。
記録のつけ方
- 日付
- 種目
- 重さ
- 回数
- メモ(体調一言)
これに◯/△/×のマークを付けるだけ。7〜10分タイマーを使い、終わったらすぐ記録。
フォームが気になる日は、同じアングルで10秒動画を残して見返します。記録があると「先週より1回ふえた」など小さな前進が見えて、やる気が戻ります。
これらはむずかしい理論ではなく、安全に、無理なく、続けるための土台です。痛みゼロのフォーム、計画的なオフ、最小記録。この3つをおさえるだけで、トレーニングはぐっと楽になります。
フォーム(可動域は痛みゼロ優先)/休養の入れ方/記録のつけ方 パーソナルジムを卒業しても、体型や筋肉量をキープできるかは、特別なことより“毎日の小さな習慣”で決まると感じています。 40〜50代は体調の波や基礎代謝の面で変化を感じやすい時期。だからこそ、無理なく ... 続きを見る
▶︎卒業後の習慣はこちら
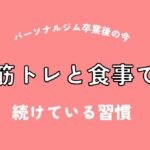
パーソナルジム卒業後の今|筋トレと食事で続けている習慣
40〜50代女性が続けやすくする実用ブロック

今日から使える“続く型”|7分or15分+週の型
STEP1|朝とトレ後はP(タンパク質)を先に確保
朝:卵1個+ヨーグルト/プロテインは表示量に従い、少量から
・トレ後:タンパク質約20g目安(例:サラダチキン半分+ゆで卵1個)
※食事が足りた日は無理に足さなくてOK(目安)
STEP2|その日の体調で“7分or15分”を選ぶ
- 7分(つかれ気味)
ヒップヒンジ20秒→休10秒→プランク20秒→休10秒×2周 - 15分(ふつうの日)
回数は各8〜12回×2セット/休60〜90秒/息を止めない
-下半身日:スクワット/ヒップリフト
-上半身日:膝つき腕立て/プランク20〜30秒
(ジム可:レッグプレス/チェストプレス/ラットプルダウンから2種)
STEP3|週の型を決めて当日判断を減らす
- 月=下半身、木=上半身(予備:土)
- 同じ部位は48〜72時間あけるを目安に
STEP4|下げるルール(続けるコツ)
- 眠れていない/だるい→7分に変更
- 関節が不安/違和感→可動域を浅く、痛みゼロで中止可
- きつすぎる →重さ−1段or回数−2
- 終わりに水分+軽いストレッチ
STEP5|“最小”記録でOK
- 日付/種目/回数(または時間)/体調ひと言+◯/△/×
- タイマーをかけて、終わったら即1行メモ
(共通)フォームは痛みゼロ最優先。息は上げるとき“フッ”、下ろすとき“スー”。翌日に張りが強く残ったら、次回は2〜3割下げます。
まとめ|知識を土台に、現場で“続く形”に育てていきましょう

ダイエット検定で学んだ基礎は、日常に落とし込んでこそ力になります。
この記事では、①朝とトレ後にP(タンパク質)を先に確保する、②負荷は「最後の2回がややきつい」を目安に日によって下げる、③週の型を決めて当日判断を減らす――という3つのコアをお伝えしました。まずはこの型に沿って、小さく始めて小さく続けることが近道です。
理論と実践がズレたら、やさしく修正すれば大丈夫です。糖質を削りすぎた日はトレ前後に少量の主食+Pへ戻す、メニューが重い日は「1種目1セットでもOK」にする――この“下げるルール”が、挫折を防ぎます。
さらに、フォームは痛みゼロ最優先/48〜72時間あける休養/1行記録というパーソナルジムでの学びをセットにすれば、手応えと継続の両立がしやすくなります。
迷う日は、7分版でも1セットでも十分です。終わったら日付と◯/△/×をメモ。「できた」を積み上げるほど、体も心も整いやすくなります。今日の自分に合った強さで、また一歩だけ前へ進みましょう。
※本記事は一般情報および筆者の体験談であり、医療的助言ではありません。体調に不安のある方は、無理をせず必要に応じて医療専門職へご相談ください。
※感じ方・結果には個人差があります。体調に合わせて量・回数・可動域・時間を調整してください。
▶︎迷わず続けるなら「週の型」をここから固定 40〜50代女性が筋トレを無理なく続けるための週3〜4のメニュー例です。 結論:レッグプレス/ラットプルダウン/チェストプレスを各8〜12回×2〜3セット(合計30〜45分)。 重さ目安は「10回で少 ... 続きを見る
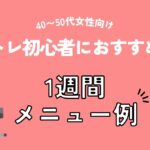
40〜50代女性向け|筋トレ初心者におすすめの1週間メニュー例
執筆:kaeco(ダイエット検定1級・2級/40〜50代向け筋トレ発信)
プロフィールはこちら